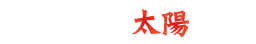ホーム >> Q & A
Q & A
Q.娘を二人持っておりますが、二人とも嫁に出しました。私ども夫婦は先祖から受け継いだ墓を守り、
その墓に入りますが、後はどうしたらいいのでしょうか。長女に任せるべきでしょうか。
Q.四十九日の法要は非常に大切だと言われていますが、どうしてですか?
Q.お葬式に友引を避けるのはどうしてですか?
Q.お寺によってご本尊が違うのはどうしてですか?
Q.仏前にお供えしてはいけないものはありますか?又、ご飯の代わりにパンをお供えしてもいいのでしょうか。
Q.三途の川を渡るのに、死者に六文銭を持たせるのはどうしてですか?
Q.古くなった御札はどうしたらいいのでしょうか。
Q.戒名は宗旨・宗派に関わらず全ての宗旨・宗派にあるのですか?
Q.お地蔵さんはどうしてよだれかけをしているのですか?
Q.骨上げはどうして二人でするのでしょうか。
A:
現在では、少なくとも法律的には長男相続とか長女相続といった事はありませんので、娘しかいないからといっても、
長女だけが先祖の墓を守る義務はありません。そこで、二人の娘さんと十分に相談した上で、例えばお墓の近所に住む娘さんがお墓を守り、
もう一人の娘さんが管理料等、経済的にある程度の額を負担する、といった様に決めておかれたらいかがでしょうか。
長女であろうと、次女であろうと、またお二人とも嫁いだのであろうと「ご先祖」ということでは全く同じです。
ぜひともお二人がいつまでも仲良く自分達のご先祖のお墓を守っていけるように、ご両親が健在のうちに話し合われたらいかがでしょうか。
もちろん、お二人のご主人様達もご一緒にお話をされるのが一番です。
A:
仏教では、人間は輪廻転生するという考え方があります。死後、次の生をうけるまでの状態を中陰(中有)といい、
この期間が四十九日間とされています。そして、七日ごとに死者の生前の罪が裁かれるということになっており、
そのため、残された者は初七日から始まり、二七日(ふたなのか)、三七日(みなのか)、四七日(よなのか)、
五七日(いつなのか)、六七日(むなのか)、そして七七日(なななのか)と七日ごとに読経をし、死者の罪が軽減され成仏できるように祈るのです。
四十九日は七回目の裁きを受け、死者の運命が定まる日です。死後の四十九日は、新たに生まれる世界が決定するので、
重要な意味を持つのです。また、初七日、二七日…七七日にはそれぞれ守り本尊があります。初七日は不動明王、
二七日は釈迦如来、三七日は文殊菩薩、四七日は普賢菩薩、五七日は地蔵菩薩、六七日は弥勒菩薩、七七日は当会のご本尊様でもある薬師如来です。
A:
友引とは六曜の一つです。六曜とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の事です。六曜は中国で生まれたとされ、
時刻の吉凶を占うものであったようです。日本に六曜が伝わったのは、鎌倉時代末期から室町時代とされます。
その名称や解釈・順序も少しずつ変えられ、現在の様になったのは、江戸時代の頃と言われています。六曜は、
本来は時刻の吉凶を問題としていますが、現在では日の吉凶として用いられるようになりました。一般的に、結婚式には仏滅を避け、
葬儀には友引を嫌っています。仏滅は物滅ともいい、実際には仏教の教理とは関係ありません。もちろん、六曜も同様です。
従って、友引も仏教とは無関係です。友引の本来の意味は、「勝負なき日と知るべし」とされ、勝負事で何事も引分けになる日、
つまり「共引」とされていました。このような意味とは違って、友引の語句から「友を引く」ということで、葬儀を避ける様になりました。
また現実的には、火葬場は友引が休日となり、火葬を必要とする葬儀は実際不可能となりました。
本来仏教にはなかった考え方が仏教の儀式に入った例と言えます。ただ、最近では友引休業を廃止している火葬場もあるようです。
A:
寺院には、その寺院が建立される経緯を記した縁起が伝えられています。その中にご本尊を祭る趣旨、祈りが記されています
。宗旨・宗派の根本経典に基づく本尊や、祖師の思想、その寺院を開いた僧侶の教元、
あるいは寺院を作ろうとした人々の願いからご本尊が決まってきます。従って、寺院によってご本尊が異なる背景は、
人々の願いが実に様々であるからであり、その根底には苦を除き、楽を願い、幸せな人生・社会を願う祈りが込められているからでしょう。
当会のご本尊は薬師如来です。
A:
先に結論から言いますと、基本的には特に仏前にお供えしてはいけないというものはないかと思われます。
よく言われることですが、花では刺のあるもの、毒々しい色をしたもの、匂いのきついもの、花粉の落ちるものは避けた方が良いとされています。
しかし、故人が生前好んでいたのであれば、それをお供えしても良いのです。また、生物もあまりお供えしない方が良いように言われますが、
やはり故人が刺身が好きだったり、肉が好きでしたら、それを仏前に上げたくなるのが家族としての当然の気持ちです。
そうした生物を仏前に上げる場合は、一度お供えしておいて、その後は家族みんなで頂くようにしたら良いでしょう。
したがって、パンをお供えしても一向に差し支えありません。ただ、大切な事は、仏前は聖なる所ですから、
汚したままにしないでいつも清潔にしておくべきだと思います。その供養の心の表れが、つまりお供えということになるのです。
A:
古代中国の習慣を見習ったものです。人は死後、亡者となって旅をして行くと考え、その旅行費用として遺族が持たせたものです。
日本では、六文入れて、それを六文銭といいました。冥土の旅は、死出の山、三途の川を越えることから始まるとされています。
三つの渡しがあるので、三途の川といいます。三つの渡しの内、上の渡瀬は浅く、罪の浅い者が渡り、中の渡瀬は金銀七宝の橋で善人だけが渡り、
下の渡瀬は悪人が渡るものです。三途とは、地獄・餓鬼・畜生の三つを指し、三悪道、三悪趣ともいい、
自分のつくった悪業の結果として苦しみを受ける境涯です。六文の「六」については、三途に阿修羅・人・天の三つを加えた六道に該当するようです。
どれも悟りきらない煩悩に苦しめられる輪廻転生の存在です。江戸時代、享保年間の頃には、この世の銭が無くなることを恐れ、
この風習は禁止されたという風聞も残っているそうです。現代では火葬の都合で紙に印刷されたものが代用されています。
A:
年の初めに一年の幸せを祈った御札はおろそかに出来ないのではないか、と思ったり、目的達成の願いが込められた御札はほおっておけない、
と考える心は大変清らかなものです。お札は求めた神社仏閣の御神体、御本尊と考えますので、近い所であれば年末にはお返しに行きます。
古くなった御札の置き場所が用意されていますので、そこへお返ししましょう。古い御札は「作法」をした後に「お焚きあげ」となります。
その他、お守りなどの扱いも皆、同様です。作法とは、御札へ迎えられた御神体、御本尊に元の世界に戻っていただく手続きです。
又、見方を変えると、願い事は御神体や御本尊と自分との約束事ともいえますから、節目毎に挨拶をするのが礼儀と言えます。
わざわざ返しに行くのは面倒だからといって、自分で燃やしてしまったり、ゴミに出したりするのは止めましょう。
自分の願いを込めた大事な物の扱いとしてはお粗末に思われます。
A:
宗派によっては法名・法号などと呼びますが、一般的には戒名と呼ばれ、仏の弟子になった事を表す名前です。
戒名の構成は院号、道号、戒名、位号となっており、宗派によって異なります。院号はもともと天皇が退位して出家したときの呼称で、
それが寺の中にある建物の別名になり、そこに住む人や建立した人にちなんでつけられたものです。道号はその人の人柄や職業、
趣味などにちなんでつけられたものです。その下につく戒名は二文字で仏教徒になった時の名前です。位号は男性の場合、
居士・信士・禅定門・童子、女性の場合、大姉・信女・禅定尼・童女などがあり、仏教徒であることを表しています。
戒名自体はどんなに人でも二文字で、仏の世界は平等であることが表現されています。しかし、お位牌に書かれた戒名は、
院号・道号・位号などのすべてが戒名と受け取られ、重々しく長いものがよいと考えられがちですが、本来戒名は二文字だけですから関係のないことなのです。また、真言宗では位牌の上部に大日如来の種子である梵字の (ア)を記します。これは等しく大日如来の弟子であることを表しているのです。
(ア)を記します。これは等しく大日如来の弟子であることを表しているのです。
 (ア)を記します。これは等しく大日如来の弟子であることを表しているのです。
(ア)を記します。これは等しく大日如来の弟子であることを表しているのです。
A:
御釈迦様が入滅されてから、未来仏である弥勒菩薩が現れるまで、56億7千万年あるといわれています。その間は仏様がいませんでした。
その間に迷っている衆生を救う為に姿を変えて現れるのがお地蔵さんです。衆生とは、この世に生を受けたもの全てを意味する仏教用語です。
お地蔵さんの事を六道(ろくどう)能化(のうけ)といいますが、それはお地蔵さんが地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天
という衆生が迷っている世界(六道)で、衆生を教え導くことに由来します。六道を救う事から六地蔵の信仰が生まれました。
中国の唐時代に、お地蔵さんは十王の思想と結びつきました。十王とは地獄で亡者の審判を行う10尊の、いわゆる裁判官的な尊格です。
この衆生の罪を責める十王に対して、六道に姿を変えて衆生を苦悩から救い、善い世界に向かわせるのがお地蔵さんです。
日本でも平安時代から鎌倉時代の初めに、賽の河原で苦しむ子供を救済する話が「地蔵和讃」によって民衆に広がりました。
このように、さまざまな信仰と結びついたお地蔵さんは、ある時は賽の河原の子供を救い、子供の成長を見守る子安地蔵として、
ある時は、村や道の守り神として道端に立っている六地蔵となり、信仰されました。よだれかけをしているのは、
子供を亡くした親が、早く自分の子をお地蔵様に救っていただきたいとの願いをかけて、子供匂いをついたものをつけたのが始まりと言われています。
また、よだれかけが一番簡単に付けやすかったから、という説もあります。
A:
火葬された遺骨を拾い上げる事を「骨上げ」あるいは「灰寄せ」「骨拾い」などと言います。火葬の風習は仏教の興ったインドからあり、
「荼毘に付す」という言葉も残っています。荼毘とは梵語で「焼く」「火葬する」という意味です。火葬後の遺族による拾骨は日本独特の
儀礼と言われています。火葬が終わると二人一組になって、故人と血の繋がりが深い人から順に箸で遺骨を拾い、骨壷へ移していきます。
昔は一人が箸で持った遺骨を順に次の人に渡していく形式でした。二人でするようになったのは、故人の霊が一人の人にとりつくのを恐れることと、
亡くなった人の死を共に悲しむためだと言われています。遺骨を骨壷に移す時に二人で一つの骨をはさむ事を「箸渡し」といいます。
「箸渡し」は「橋渡し」に通じると考えられ、この世からあの世へと三途の川を渡してあげるという思いから来ていると言われています。
故人を皆で送ってあげようよいう気持ちの現れでしょう。